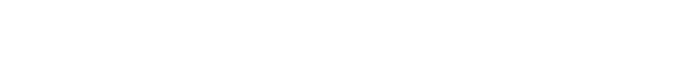“Jホラーを知り尽くした男たち”が明かす、Jホラーの知られざる舞台裏!
今回は《特別編》『ザ・ミソジニー』応援企画!
「高橋洋×鶴田法男スペシャル・ホラー対談①~読者プレゼント付き!~」
(2022年9月22日掲載)
人気連載企画『Jホラーのすべて 鶴田法男』は《特別編》。公開中の『ザ・ミソジニー』応援企画「高橋洋×鶴田法男スペシャル・ホラー対談」①を掲載します。
さらに抽選で二名様にお二人のサイン入りパンフレットをプレゼントします(応募方法は記事の後半に掲載)。

<バックナンバー>
序章「監督引退」
第一回「原点① …幽霊を見た… 」
第二回「原点② 異常に怖かった」
第三話「オリジナルビデオ版『ほん怖』誕生」
第四回「幻の『霊のうごめく家』初稿」
第五回「OV版『ほん怖』撮影秘話①」
第六回「誕生!“赤い服の女の霊”の真相(前編)OV版『ほん怖』撮影秘話②」
第七回「誕生!“赤い服の女の霊”の真相(後編)OV版『ほん怖』撮影秘話③」
第八回「検証!伝説的傑作『霊のうごめく家』はいかにして生まれたのか?(前編)~OV版『ほん怖』撮影秘話④~」
第九回「検証!伝説的傑作『霊のうごめく家』はいかにして生まれたのか?(後編)~OV版『ほん怖』撮影秘話⑤~」
第十回「フジテレビ版『ほんとにあった怖い話』誕生秘話~」

今回のスペシャル・ゲスト、高橋洋監督長編最新作『ザ・ミソジニー』絶賛公開中!
不気味な洋館、呪われた事件を演じる二人の女優。
彼女たちに憑依したのは「役」なのか「霊」なのか
『リング』の脚本などを手掛け、Jホラーを語るうえで欠かせない人物であり、監督としても異色作を連発する鬼才、高橋洋の最新監督作『ザ・ミソジニー』が9月9日(金)よりシネマカリテほかにて全国順次公開中だ。
高橋監督は90年に脚本家としてデビュー後、中田秀夫監督『女優霊』(95)『リング』(98)『リング2』(99)や、鶴田法男監督『リング0 バースデイ』(00)などの脚本を手掛け、 世界中にJホラーブームを巻き起こした。
04年に『ソドムの市』で初長編を監督。その後もコンスタントに監督作を発表し続け、18年は監督作『霊的ボリシェヴィキ』を公開。『ザ・ミソジニー』は4年ぶりの長編最新作となり、中原翔子、河野知美、横井翔二郎らが出演する。

『ザ・ミソジニー』本予告編
「Jホラーのすべて」《特別編》
映画『ザ・ミソジニー』応援企画
高橋洋×鶴田法男スペシャル・ホラー対談①

高橋洋: 先日は、OV版『ほん怖(「ほんとにあった怖い話」【新装版】)』DVDの特典で、鶴田さんと対談させていただいて。
鶴田法男: その節は大変お世話になりました。高橋さんほか皆さんとの対談を特典に収録して発売すると発表した途端にSNSで凄い拡散されて、お陰様で無事に発売できます(2022年10月28日発売)。
高橋: トーク部分をあんなに使ってもらえるとは思わなかったので、ちょっとびっくりしました(笑)。
鶴田: 貴重なお話が多かったので、目一杯使わせていただきました(笑)。ありがとうございます。
…それで、実はWEB映画マガジン「cowai」の中で、私が「Jホラーのすべて」という非常に大それたタイトルで(笑)不定期連載をしていて、そこで高橋さんとの対談ができないかと思ったんです。ちょうど公開中の『ザ・ミソジニー』の応援企画として。まず僕の感想は、「『ザ・ミソジニー』が高橋洋の最高傑作なのではないか」と思ったんですよ。

高橋: ありがとうございます。
鶴田: ご自身の感触としてはどうなんですかね。
高橋: 僕にとっては贅沢な環境で撮らしてもらえたんで、とても嬉しいんですけど…。ただ低予算だけにワン・セットで撮るプラスαぐらいのことしか出来ないから、ちょっと実験的にやっていかないと、もたないかなっていうのがあって。だから、あえてわかりにくいというか、(普通の)物語の関節を外すような作り方をしています。それが皆さんにどう受け入れられるのかっていうのが一番心配なところですね。
鶴田: いやいや。僕は正直な話をすると、今までの高橋洋作品の中で、一番わかりやすい…というか、なんか見てて腑に落ちる作品だったんです。
高橋: ほんとですか。
鶴田: なぜ、そう思ったかっていうと、実は『リング0 バースデイ』(監督・鶴田、脚本・高橋)をご一緒させていただいた時、高橋さんが何回目かに書き上げてきた稿が理解できなかったんすよ。
高橋: はいはい。
鶴田: 『リング0』は高橋さんの作品だと思ってたから、これでも「撮れ」と言われたら撮ろうと思って覚悟してたんだけど、プロデューサーの小川真司さんと話したら、小川さんも「これはよくわからない」って言うわけですよ。それで「高橋さん、すみません、よくわからないです」って直接言って。いまだによく覚えてるのは確か、貞子が何かする時に空中に歯車が現れて……。
高橋: 何が現れた?
鶴田: 歯車。大きな歯車が現れて、それが空中で回転しているっていうイメージが書かれていたんですよ。
高橋: それは多分、僕が幻視したものですね。
鶴田: 幻視ですか。
高橋: 金縛りにあった時、無理やり目を開けると見える、時々変なものが見えたりする…脳内のちょっとした幻想だと思います。歯車は……赤ちゃんのベビーベッドの上で回ってるガラガラみたいな。
鶴田: あれ、なんていうんですかね。
――確認したら、「ベッドメリー」「ベビーメリー」だそうです。
高橋: それだ。天井で回っている、そのすごいでっかいバージョンで全部出刃包丁がぶら下がってるってのが暗がりの中グルグル回転してるのを、昔見たことがあって。
鶴田: へえ。
高橋: それを苦し紛れに書いたんで……。
鶴田: 『リング0』の時は正直、高橋さんも(『リング』シリーズが)3作目で、大変だったと思うんです。でも角川映画的にはやっぱりヒットさせないといけない。だから貞子の青春映画が基本コンセプトなんだけど、プラスちゃんと怖くしないとダメだった。だから、初期の頃の脚本は青春ドラマとしてはうまく出来てたんだけど、「これあんまり怖くないよね」って話になっちゃってた。高橋さんも「うーん」って悩まれたんでしょう。いろんな怖いと思えることをとにかく詰め込んできたんだけど、そしたら訳わからないっていう問題が生じて(笑)。それで監督、プロデューサー陣で話し合った上で「高橋さん、すいません、よくわかんないっす」って話になって、高橋さんもまた悩んじゃってね。
でも、高橋さんが「怖い」と思われることがいっぱい詰め込まれていて、それはそれで面白かった。ただ、僕はこれを撮れる自信が全くなかったですね。だから高橋さんに「ごめんなさい」って。
高橋: ああ、そうでしたか。
鶴田: で、『ザ・ミソジニー』を見た時も、今、高橋さんが自分で思う「怖い」とか「面白い」と思えることを、あの1セットと限られた登場人物という低予算の条件の中で、やれることを全部詰め込んだなって。ある意味で、これは高橋洋の集大成になっていると思ったんです。

鶴田: 例えば『旧支配者のキャロル』とか、その他の(過去の監督)作品を見てきた時、やっぱり低予算の中でどう撮るかって、おそらく悩まれたんだろうけど、今までの作品というのは、低予算を逆手に取って楽しんで作っているけど、一方で、開き直ってる感じが僕はしていたんです。でも、『ザ・ミソジニー』も低予算の中でもちろん楽しんでるし、ある意味開き直ってる部分もあるけど、それだけじゃない、お客さんをしっかり楽しませていくっていう、なんかそういう気概みたいなのが感じられたんです。すごく高橋洋の作品なんだけれども、同時に『ザ・ミソジニー』と言う独立した作品として、すごく優れてるんじゃないかって、僕は見終わった時思ったんですね。だから「感触的にどうですか」って聞いちゃったんです。
高橋: いや、そんなに肯定的だとは思わなかった。でも『リング0』の話で思い出したんだけど、あれホン(脚本)作りですごい苦しんでいて、確か僕が書いてきた何稿目かで、鶴田さんから「登場人物が多重人格に見える」と言われた。あるシーンで示している人格と、別のシーンで示している人格が全然違う。「そこ、何とか直りませんかね」みたいな話をされた時、「うん、そうだよね」と思って直したと思うんだけど。登場人物が二重人格に見えるって言われたことは、すごく印象深くて。それは「この野郎!」って怒ってるんじゃなくて、ひょっとしたら俺ってそうなっちゃうのかも、みたいな。1人の人物が、何か一つの人格の中に収まらないような物の見方をしているのかもしれないって、鶴田さんに言われて、はっと気づいた。もう普段はやっちゃいけないんだけど、「これ(『ザ・ミソジニー』)はやっていいよね」みたいな。こう言うとプロデューサーの河野さんが怒るかもしれないけど、それができた、(そういう意味での)物語の関節を外すことができたっていうのは一回やれて良かったな、その手ごたえはすごくあるんですよ。

「心霊実話テイストの物語を、頭から壊していかなきゃいけなかった。」(高橋洋)

鶴田: あともう一つ思ったのは、その二重人格と関わってくるんですが、人間がお芝居をする時、役の人格と本来の人格があって、演じるということは二重人格と言えなくもない。そこのところの高橋さんのこだわりとして、『リング0』って劇団「飛翔」という劇団が設定としてある。実はご一緒させていただいた『おろち』も映画俳優の設定なんですよね。
高橋: そうですね。
鶴田: 『旧支配者のキャロル』は映画作りをしているという、映画の世界の中の話になっていて、今回もまたそういう話になってくると思うんですけど、そこの部分の高橋さんのこだわりというかテーマ性というか。
高橋: そう。よく、メタ構造ってことが持て囃された時期があったでしょう。僕自身も「きっとこれはメタ構造に自分が引っ張られてるんだろうな」って思ってやってた頃があったんですけど、よくよく考えると、いや、そうじゃなくて、メタ構造にして複雑にしたいっていうより、演劇も含めた虚構を直接、映画に撮りたいんだっていう、その見世物(の精神)ですよね。なにより見世物をやっているところを撮りたいみたいな。きっとそういうのもあるんじゃないかなって、最近は思います。映画にはそもそも見世物なんだという、自分の出自を写し込みたいな欲望があるんじゃないか。それをやると映画が妙に活気づく気がするんですね。結局は、それをメタ構造って言われればそうなんだけど、いや、そのメタ構造にするっていうのは、何か斬新な構成を考えてじゃなくて、自分が一番興奮する大前提になっているプロセスなんじゃないかな、きっと。

鶴田: 今年僕、『六番目の小夜子』というお芝居をやらせていただいて。
高橋: はい
鶴田: 高橋さんも見てくださってね。高橋さんがすごい素晴らしい感想おっしゃってくださった。それは「グラン・ギニョールってこういうことだったのかな」みたいなことを見終わった後おっしゃってくださって(※19世紀末から20世紀半ばに存在したパリの大衆演技・見世物小屋のグラン・ギニョール劇場のこと。ホラーや猟奇的なテーマが多く、血みどろの特殊効果、特殊造形なども駆使され、ホラー映画にも多大な影響を与えた)。いやもう、そう言ってくれるの、ほんと嬉しかった。生の舞台で表現できることって何だろうって思った時、僕はやはり「幽霊を見たときの感触」っていうのを、劇場に来てくれたお客さんに生々しく伝えたかった。それをやってみようと取り組んだのが舞台の『六番目の小夜子』だったんですね、まさに。だからグラン・ギニョールって、おそらく恐ろしいものを、ナマで見せていくことだったわけじゃないですか。だから高橋さんの今回の『ザ・ミソジニー』って、それを映画でやったらどうなるかってことを突き詰めた帰結なのかな、みたいな感じが、僕はちょっとしたんです。

高橋 『六番目の小夜子』って、今年でしたっけ。
鶴田: 1月ですね。
高橋: すごい前のような気がするけど(笑)。大半のお客さんはグラン・ギニョール自体知らないでしょうけど。
――知識として知っていても、ほとんどの人は実際に観劇していないですから。
高橋: そうですよね。100年近く前にすごい隆盛を極めた、残酷劇ですよね。市井の事件をグロテスクに再現するみたいな。物見高い人たちがそういう猟奇的な事件を疑似的に体験するために見に行くみたいな。確か60年代、70年代くらいまで劇場があったんだけども、その後なくなってしまって。辛うじて残っている舞台写真とかあと何本か台本が翻訳されていて、それでしか知りえなかったんだけど、『六番目の小夜子』で新国立劇場に行ってみて、「ああこういうことかもしれない」って。恐怖劇を生で見ることって、そうそうないですよね。まあ、『四谷怪談』とか歌舞伎で見るしかないですよね。
鶴田: 役者がその舞台空間に出てきて別人格を演じるものを、我々は劇として見るっていうのが基本にあるんだけれど、そこに存在している劇は、リアルな空間の中で行われているから、ある種のドキュメンタリーを見ているようなことになってくるわけじゃないですか。それを映画でやろうとした時、こういうこと(『ザ・ミソジニー』)になってくるのかなって。もちろんそこに中原翔子さんや河野知美さんっていう、リアルな女優さんがいるわけで、ナオミとミズキという役を演じてるんだけど、ナオミとミズキが、さらにまた別の人格を演じていくことで、非常に複雑なことになる。だから見ているこっちがものすごく混乱するんですけど、でもその混乱は、ある種のドキュメンタリー性を生んでいると、僕には思えたんですね。
高橋: 前から思っていたんですけど、マノエル・ド・オリヴェイラが作る映画のコンセプト(キャメラの前で上演された演劇)って、いわゆる舞台を単にキャメラに収めるっていう意味じゃなくて、キャメラの前で虚構を演じる、その記録だっていう。鶴田さんがおっしゃるように、それってドキュメンタリーですよね。僕も、そうした舞台で、何かが起こるんじゃないか、みたいなことは、やりたいんですよね。もう映画のタイトル忘れちゃってるけど、ジキルとハイド物の映画で、切り裂きジャックとミックスした内容だったけど、その中の劇中劇で「ジキルとハイド」の舞台が入っている。大勢の観客の前で、ステージのジキルが薬飲んで変身してくんだけど、80年代の映画だからSFXで顔がこう歪んで、こう変形して、それを観客が見て絶叫するんです。本来おかしいですよね、舞台なのに(笑)。でも、それが妙に面白かったんです。(その後、タイトルが『切り裂きジャック』(1988 監督:デヴィッド・ウィックス)と判明)。
鶴田: なるほど。
高橋: そういうことにすごく惹かれてるんですよね
鶴田: わかります(うなずく)。
『ザ・ミソジニー』に関して言うと、今回はあそこのロケ場所の存在は大きいですよね。これも河野さんが見つけてきたんですか。

高橋: そうです。最初、僕はホン(脚本)が書けなくて。書けないっていうのは、河野さんと中原さんの出演が決まっていたんだけど、二人の個性が強烈で、なんか普通の人が心霊現象に出会って「ひーっ!」みたいな作り方にならないと思って(笑)。最初から、とんでもない2人がいるっていう、『悪魔のような女』の作り方を進めざるを得ないから、世の中の人が求めているであろう、心霊実話テイストの物語って、頭から壊していかなきゃいけなかった。じゃあ、怖く見せるにはどうやったらいいかなって、悩んでる時、河野さんが「いい物件あるから見に行きましょう」って、シナハンがてら見に行った。そうしたら、すごく良くて、いくつかのシーンが浮かんできて、もう場所に合わせて、場所の当て書きみたいな形で(脚本を)作ったんですよね。あの場所をフルに使うという、動機付けが与えられたから、ホンができたようなもんですね。何もなかったら、どういうお話にしていいか、ちょっとわかんなかったかもしれない。
鶴田: 企画の発端は、河野さんと中原さんが、高橋さんに何か作ってもらおうみたいなことから?
高橋: 河野さんがエグゼクティブプロデューサーで、言い出しっぺです。共演として、彼女が中原翔子さんと組みたいって言って連絡して、メインキャストが先に決まった。それで踏み出したんです。やるとしたら、この女2人の何かおぞましい世界だろう。普通の女性が何かに怯える…といった、よくある安定したゴースト・ストーリーにはならないと思っていた。

鶴田: それはお話いただいてから、シナハンに行ってホンができるまで、どれぐらいの期間がかかったんですか。
高橋: 去年の6月に撮ったんですけど、話があったのはその前の年の年末ぐらい。それで(脚本で)うんうんうなって、「書けない書けない」って、シナハンに行ったのは、けっこう直前の4月ぐらい。
それで大慌てで書いたので、たぶん執筆期間そのものはひと月とかそんなんじゃないでしょうか。
鶴田: “きっかけ”が見つかるまでが大変ですよね。
高橋: そうですね。『うそつきジャンヌダルク』と並行してやってたんで。5月に『うそつきジャンヌダルク』を撮影して6月が『ザ・ミソジニー』だったので、かなり大変だったんですよ。準備やりながら撮影してるっていう、よくあんなことができたなって感じでしたね。
鶴田: 過去に高橋さんと何度も仕事をさせていただいて、でも『リング0』が一番大変だったんだけど、お悩みになると本当に悩まれる。
高橋: 悩むんですよね。
鶴田: だから、これ、どれぐらいの期間でお作りになったのかなって。
高橋: まあ、『リング0』の頃はね、それ1本で集中してやってたから、今考えるとすごい贅沢な悩み方をしていた。
なんか今は…歳とると用事多いですよね(笑)。不思議なくらい用事が多い。だからいろいろ重なって、撮影の前後はえらいことでした。
鶴田: 『リング0』の頃と違って、今は場合によっては自分でお金出さないと作れないみたいなことになってきちゃってるから(笑)。そうすると、どうしてもいろいろと対応しないといけないことが増えちゃって、それだけで時間がかかっちゃう。厳しいですよね。高橋さんもご苦労なさっている。
<つづく>
次回は9月23日(金)夜の予定です。
【『ザ・ミソジニー』関連インタビュー】
【読者プレゼント】
映画『ザ・ミソジニー』
サイン入りパンフレットを抽選で二名様にプレゼント!

<応募方法>
応募締め切りは2022年9月30日(土)
応募方法は、WEB映画マガジン「cowai」twitter公式アカウント(@cowai_movie)をフォローし、該当するプレゼント記事ツイート( https://twitter.com/cowai_movie/status/1572975897241849856 )。
<抽選結果>
締め切り後に抽選を行い、当選された方に「cowai」公式TwitterアカウントよりDMで通知させていただきます。
当選品の色紙は宅急便で発送する予定です。(諸般の事情や、災害、キャンセル発生等やむを得ぬ事情で遅れる場合があります)
皆様のご応募お待ちしています!
【応募の注意点】
〇当選後に住所の送付が可能な方のみご応募ください(日本国内のみ有効)。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。
〇当選品のパンフレットは劇場でも販売されていますが、今回のプレゼントは映画配給会社よりご提供いただいたプロモーション目的の非売品扱いとなります。このため、傷や汚れ等があっても交換はできませんので、ご了承ください。
※非売品につき転売目的のご応募は禁止とさせていただきます。
〇当選のキャンセルが発生した場合は再度抽選を行う場合があります。
〇抽選結果や抽選経過に関して個別のお問い合わせには応じられませんので、あらかじめご了承ください。
【高橋洋プロフィール】

1959年生まれ。90年に脚本家としてデビュー後、中田秀夫監督『女優霊』(95)『リング』(98)『リング2』(99)、鶴田法男監督『リング0 バースデイ』(00)などの脚本を手掛け、 世界中にJホラーブームを巻き起こした。
04年に『ソドムの市』で初長編を監督。その後『狂気の海』(07)、『恐怖』(10)、『旧支配者のキャロル』(11)と監督作を発表。 17年には黒沢清監督『予兆 散歩する侵略者』の脚本を手掛け、 18年は監督作『霊的ボリシェヴィキ』を公開。21〜22年は『うそつきジャンヌ・ダルク』、『同志アナスタシア』を監督し、オンラインで現在公開中。
【鶴田法男プロフィール】

1960年12月30日、東京生まれ。和光大学経済学部卒。
「Jホラーの父」と呼ばれる。大学卒業後、映画配給会社などに勤務するが脱サラ。
1991年に自ら企画した同名コミックのビデオ映画『ほんとにあった怖い話』でプロ監督デビュー。本作が後に世界を席巻するJホラー『リング』(98)、『回路』(01)、『THE JUON/呪怨』(04)などに多大な影響を与え、‘99年より同名タイトルでテレビ化されて日本の子供たちの80%が視聴する人気番組になっている。
2007年には米国のテレビ・シリーズ『Masters Of Horror 2』の一編『ドリーム・クルーズ』(日本では劇場公開)を撮り全米進出。
2009年、「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」コンペティション部門審査員。
2010年より「三鷹コミュニティシネマ映画祭」スーパーバイザーを務める。
角川つばさ文庫『恐怖コレクター』シリーズ他で小説家としても活躍中。
フライヤー


『ザ・ミソジニー』サウンドトラック SOUNDCLOUDにて公開中
STORY

女優で劇作家のナオミ(中原翔子)は一夏借りた山荘で、かつて自分の夫を略奪した女優ミズキ(河野知美)を呼び寄せ、芝居の稽古を始める。題材となるのはある謎めいた母親殺しの事件だった。マネージャーの大牟田(横井翔二郎)と共にやって来たミズキは、母親を殺した娘の役を演じるにつれ、事件が起きたのはこの屋敷ではないかと疑い始める….。

※ミソジニー(英: misogyny):一般的には「女性嫌悪」「女性蔑視」と訳される。その根幹にあるのは、男性支配の秩序から女性が逸脱することへの強い抵抗や反発だとされ、広い意味での偏見や性差別とは異なる。男性のみならず、女性にも見られる心的傾向と言われる。
『ザ・ミソジニー』特報予告編
高橋洋監督作品
【作品概要】

『ザ・ミソジニー』
2022年/日本/77分/カラー/シネマスコープ/ステレオ/DCP/映倫G
出演:中原翔子 河野知美 横井翔二郎 浅田麻衣 内田周作 羽柴有吾 根津麻里亜 大橋将太郎 古山憲太郎
脚本・監督:高橋洋 企画・エグゼクティブプロデューサー:河野知美(古山知美) ラインプロデューサー:大日方教史 助監督:海野敦 撮影:中瀬慧 照明:玉川直人 音響:川口陽一 美術:山本直輝 スタイリングディレクター:藤崎コウイチ 編集:木田龍馬 音楽:長嶌寛幸
製作・配給:『ザ・ミソジニー』フィルムパートナーズ/屋号 河野知美 映画製作団体/Ihr HERz株式会社 配給協力・宣伝:プレイタイム
© 2022『ザ・ミソジニー』フィルムパートナーズ
■公式サイト:misogyny-movie.com
■Twitter:@TakahashiHorror
■Instagram:takahashihorror
9月9日(金) シネマカリテほか全国順次ロードショー
【鶴田法男監督最新作『戦慄のリンク』】
Jホラーの父が仕掛けた、
ネット小説が洗脳する恐怖の深淵を描くAIサスペンス・スリラー
1990年代初頭、ビデオ映画「ほんとにあった怖い話」(現・フジテレビでドラマ化。記事後半に最新情報あり)を手掛け、世界を席巻するJホラーを生んだ監督たちに多大なる影響を与えた“Jホラーの父”であり、関連シリーズ76万部突破「恐怖コレクター」の小説家でもある、『リング0』『おろち』の鶴田法男監督。
当サイトでも「Jホラーのすべて 鶴田法男」を好評連載中の彼が中国で新たに仕掛けた、AIサスペンス・スリラー『戦慄のリンク』(原題・網路凶鈴)が、12月23日(金)より新宿シネマカリテほか全国ロードショーが決定し、日本版ポスターの解禁となった。
この度、公開決定と共に、ポスタービジュアル&予告編が解禁された。

INTRODUCTION

中国の小説家マー・ボオンの原作を基に、SNSなどを介して参加者を洗脳し自殺に扇動するなど、ロシアから世界を巻き込んで大問題となった青い鯨(ブルーホエール・チャレンジ)事件からインスピレーションを受け、ネット小説を読んだ人たちの無残な死を迎える事件を解明しようとする若者たちを描き、新たなるサスペンス・スリラーを誕生させました。

ネット小説に仕組まれた恐怖が、読んだ人間の心理を利用し、無意識の感覚に恐怖を増大させて死を迎えさせる。映画本編に仕組まれたギミック映像とともに、恐怖の謎が解き明かされる本作のイメージを、日本版ポスターに投影させている。

主演は、台湾の人気男優で『返校~言葉の消えた日』やジャッキー・チェン製作の中国ドラマ「成化十四年〜都に咲く秘密〜」のフー・モンポーと、有名ブランドのモデルやNetflix「流星花園2018」ほか映像ドラマで活躍する中国若手期待の女優スン・イハン。スタッフには、撮影に「鎌倉殿の13人」『曇天に笑う』の神田創、編集を『クライマーズ・ハイ』の須永弘志、音響効果に『事故物件 恐い間取り』の大河原将、照明を『私はいったい何と闘っているのか』の丸山和志、そして音楽をアニメ「約束のネバーランド」の小畑貴裕と日本の敏腕スタッフたちが集結している。

STORY

大学生のジョウ・シャオノア(スン・イハン)は、前日に電話で話した従姉のタン・ジンが自殺したことが信じられず、従姉の大学の同級生で犯罪心理学に詳しい記者志望のマー・ミン(フー・モンポー)に相談する。タン・ジンのパソコンを調べることにしたシャオノアは、ショウ・ナという女性とのチャットのやりとりと、貼られたリンクからネット小説「残星楼」の存在を知る。シャオノアはそのネット小説を読むが、突然、自分の名前を呼ぶ謎の声と“髪の長い女”が現れ、得体のしれない恐怖に襲われる。シャオノアはマー・ミンとともにネット小説の謎を探るが、やがて「残星楼」に関わっていたメンバーが次々に自殺していることを知る。そして二人にも死の恐怖が忍び寄る・・・

鶴田法男の伝説的傑作OV『ほんとあった怖い話』新装版DVDで10月28日(金)発売決定!
特典は伊藤潤二、高橋洋、石井てるよし、伴大介ら豪華対談やオーディオコメンタリー!

当サイトで好評連載中の「Jホラーのすべて 鶴田法男」でも何度も紹介されている、Jホラーの原点にして最高傑作、『リング』『呪怨』『回路』などに多大な影響を与えた伝説的傑作『ほんとにあった怖い話』(オリジナルビデオ版)シリーズ(1991年・1992年)全3作の新装版DVDが、本作の公開のタイミングに合わせて、2022年10月28日(金)に発売される。

『戦慄のリンク』作品情報

〇スタッフ
監督:鶴田法男 脚本:ヤン・ヤン 原作:マ・ボヨン「她死在QQ上」
撮影:神田創 編集:須永弘志 美術:リー・チア 音響効果:大河原将 照明:丸山和志 音楽:小畑貴裕
○キャスト
スン・イハン フー・モンポー
シャオ・ハン チャン・ユンイン ウォン・マンディ ハン・チウチ ジョウ・ハオトン
提供:三鷹オスカー/フィールドワークス
配給・宣伝:フリーマン・オフィス
BD・DCP アメリカンビスタ 音声:北京語
映倫:G
原題:網路凶鈴 The Perilous Internet Ring ©2020伊梨大盛传奇影业有限公司
製作:2020年 中国 96分
12月23日(金)より新宿シネマカリテほか全国ロードショー!
【過去の関連記事】